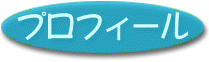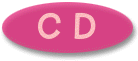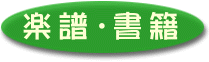藍川由美と歌う「日本のうた」
藍川由美と歌う「日本のうた」 
――「日本の歌」の謎を解く!―― 2004年3月13日(土)16:30開場/17:00開演 月見の里学遊館 うさぎホール TEL.0538-49-3400
いわき市立草野心平記念文学館/企画展 『童心の詩人 野口雨情』 2000年7月1日(土)〜8月27日(日)/9時〜17時(入館は16:30まで)月曜休館 記念講演会「音楽からみた野口雨情」 入場料:入館料のみ(一般420円/高・高専・大生310円/小・中生150円) JR常磐線「いわき」駅より車で20分or磐越東線「小川郷」駅より車で5分orいわき中央I.C.から約15分
東京文化会館レクチャーコンサート
〜「日本のうた」を歌ってみよう〜 翻訳唱歌「故郷の空」
日時:2000年2月2日(水)18:30〜 会場:東京文化会館小ホール 入場料:2,000円 主催:東京文化会館・東京都教育委員会
『荒城の月』『しゃぼん玉』『赤い靴』『てるてる坊主』『春の小川』他
日時:2000年8月27日(日)13:30〜
会場&主催:いわき市立草野心平記念文学館
いわき市小川町高萩字下夕道1−39/TEL.0246−83−0005
野口雨情は、日本の歌における三大詩人の一人として高い評価を受けています。
「赤い靴」「七つの子」「シャボン玉」をはじめとする童謡、「波浮の港」といった新民謡は、なぜこれほど愛唱されてきたのでしょうか?
その魅力を、雨情の理念や人生、さらに「船頭小唄」の作曲者・中山晋平、「十五夜お月さん」の作曲者・本居長世らと絡めつつ、実演を交えながら語りたいと思います。 音楽の広場
音楽の広場 
日本の近代音楽史・うたの百年
中學唱歌「荒城の月」
文部省唱歌「村の鍛冶屋」「春の小川」
劇中歌「カチューシャの唄」
童謡「赤い靴」「證城寺の狸囃子」
流行歌「船頭小唄」
國民歌謠「春の唄」ほか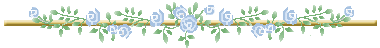
明治以降の「日本のうた」は、それまでの伝統的な音楽とは無関係に挿し木されたものだ。しかし、民族本来の歌好きゆえか、学校教育の成果によってか、「日本のうた」はその全貌を把握するのが困難なほど、さまざまな形で根を張りめぐらし、花を咲かせてきた。
最初期こそ、讃美歌や愛唱歌に日本語の歌詞をあてはめていたが、日本人はすぐに作詞・作曲を手がけるようになり、明治43年には全編邦人作品による教科書『尋常小学読本唱歌』が発行された。明治35年の教科書事件によって、この時期、小学校教材の著作権が文部省に帰属していたことから、これらの歌の作者名は伏せられ、便宜上「文部省唱歌」と呼ばれた。
一方、官製の「文部省唱歌」に不満を持つ詩人や小説家らが結集して旗揚げしたのが童謡雑誌『赤い鳥』(大正7年7月創刊)で、これ以後、類似誌の創刊が相次いだ。ただし、西條八十の証言によると、『赤い鳥』の主宰・鈴木三重吉は「歌われる童謡」を目指したわけではなく、成田為三が作曲した《かなりや》(大正8年5月号)の成功が起爆剤になったらしい。
そんな童謡運動の中でも、野口雨情と中山晋平を擁する『金の船(のち「金の星」)』(大正8年10月創刊)からは、多くの歌われる童謡が生まれている。このコンビはまた、大正10年の《船頭小唄》や昭和2年の《波浮の港》を大ヒットさせたことで流行歌の祖ともいわれた。
すでに大正3年に《カチューシャの唄》で世に出ていた中山晋平は、昭和初期に西條八十とのコンビで《東京行進曲》《東京音頭》などを大ヒットさせてもおり、童謡も流行歌も、彼抜きには語れない。
さて、この時期、巷にはエロ・グロ・ナンセンス的な歌や、新民謡・ご当地ソングによる集団的狂舞が溢れていた。大正12年の関東大震災や昭和2年の金融恐慌の影響に加え、ファッショ化への息詰まるような社会情勢に対する反発が、民衆を本能的に現実逃避へと向かわせたのかもしれない。
こうした「流行歌」と一線を画すべく、放送局では「歌謡曲」と称して、家族みんなで歌える明るいホームソングを作ろうと、昭和11年の4月と5月に「新歌謡曲」という番組を放送。6月からは「国民歌謡」という番組名で、《椰子の実》《春の唄》などの新作を発表していった。
だが、昭和12年7月の蘆溝橋事件をきっかけに番組の方針も変更を余儀なくされる。戦争の長期化に伴い、次第に戦時色が濃くなっていくのを誰も止められず、番組名も「われらのうた」「国民合唱」と変わった。そして、この、放送局による歌の歴史は、敗戦後の「ラジオ歌謡」を経て、現在の「みんなのうた」まで続いている。
その後、「日本のうた」は、諸外国の影響を受けつつ、さらに多様化している。
われわれは、そこに、「うた」は常に歴史とともにあることを、見る。
「文部省唱歌」の本当の作曲者は誰なのか? 日本のうたは、はたして正しく歌い継がれているのだろうか? …そんな素朴な疑問を、実際の演奏を交えながら検証していきます。 日時:1999年6月19日(土)午後2時〜4時(受付は午後1時より) 会場:神奈川県民ホール 小ホール (定員400名) 受講料:1,000円(当日払い)※かながわアーツ倶楽部会員の方は800円です。 お申込み・お問合せ(お電話にて下記までお申込みください。 主催:財団法人 神奈川芸術文化財団 日本歌曲のうら・おもて
日本歌曲のうら・おもて  歌曲と歌謡曲の違いは何なのか?誰がそのようなジャンル分けをしているのか?
歌曲と歌謡曲の違いは何なのか?誰がそのようなジャンル分けをしているのか?
(財)神奈川芸術文化財団 企画課 講座係
TEL.045−662−5901