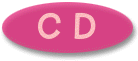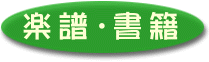――少國民のうた特集――
 2005年2月10日(木) 19:00〜/東京文化会館小ホール
2005年2月10日(木) 19:00〜/東京文化会館小ホール

 2005年2月10日(木) 19:00〜/東京文化会館小ホール
2005年2月10日(木) 19:00〜/東京文化会館小ホール

 050−7511−8457
050−7511−8457海ゆかば (大伴家持/信時 潔) 空の神兵 ―― 落下傘部隊に捧ぐ (梅木三郎/高木東六) 朝だ元氣で (八十島 稔/飯田信夫) 僕らの團結 (勝 承夫/信時 潔) 子を頌ふ (城 左門/深井史郎) 空の父・空の兄 (輿田準一/名倉 晰) 僕は空へ君は海へ (サトウハチロー/佐々木すぐる) 兵隊さんよありがたう (東京・大阪朝日懸賞人選歌/佐々木すぐる) 勝ちぬく僕等少國民 (上村数馬/橋本國彦) 山小舎の灯 (米山正夫) 想い出は雲に似て (米山正夫) 緑の牧場 (松坂直美/江口夜詩) さくら貝の歌 (土屋花情/八洲秀章) 砂山の花 (保科義雄/八洲秀章) チャペルの鐘 (和田隆夫/八洲秀章) リラの花咲く頃 (寺尾智沙/田村しげる) さざん花の歌 (寺尾智沙/田村しげる) 美しい時の流れに (藪田義雄/團 伊玖磨) 花の街 (江間章子/團 伊玖磨) |
戦時下の歌をうたうようになって初めて「少國民」という言葉を知った。 「少國民」については、次のように、國民学校で軍國教育を受けた児童との説明が多かった。 |
 2004年2月2日(月) 19:00〜/東京文化会館小ホール
2004年2月2日(月) 19:00〜/東京文化会館小ホール

 050−7511−8457
050−7511−8457心のふるさと (大木惇夫・江口夜詩) 愛國の花 (福田正夫・古関裕而) 海ゆかば (大伴家持・信時 潔) 出征兵士を送る歌 (生田大三郎・林 伊佐緒) 空の神兵――落下傘部隊に捧ぐ (梅木三郎・高木東六) 雲のふるさと (大木惇夫・古賀政男) やすらいの歌 (百田宗治・古賀政男) 勝利の日まで (サトウ ハチロー・古賀政男) 空の父・空の兄 (與田準一・名倉 晰)
大日本の歌 (芳賀秀次郎・橋本國彦) 學徒進軍歌 (西條八十・橋本國彦) 戰ふ花 (深尾須磨子・橋本國彦) 勝ちぬく僕等少國民 (上村數馬・橋本國彦) 朝はどこから (森まさる・橋本國彦) 乙女雲 (藤浦 洸・橋本國彦) アカシヤの花 (松坂直美・橋本國彦) 舞――六代目菊五郎の娘道成寺によせて (深尾須磨子・橋本國彦) |
|
今年9月14日に橋本國彦(1904-49)は生誕百年を迎える。同年生まれの作曲家に、古賀政男(1904-78)や、未だ現役の高木東六らがいる。ただし私は、古賀政男の生誕百年を昨秋とし、それまでにオリジナル編成で古賀メロディーを録音してヨーロッパで発売するという計画を立てた。生誕百年というと、わが国では、西欧文化系は満年齢を、伝統邦楽や歌舞伎など日本文化系は数え年を用いることが多い。それで同い年ながら、昨年は古賀作品、今年は橋本作品の再評価に挑むことにした。 私はすでに国内盤で『橋本國彦歌曲集』を出しているが、昨年、橋本の『四季の組曲』中で欠けていた曲が発見されたため、その全曲演奏に取り組みたいと考えた。けれど、橋本作品に興味を持たれる方はまだまだ少なく、個展を企画する勇気が出なかった。ともかく、日本人は有名人が好きだ。橋本がどれほど才能に満ちた作曲家であっても、名前を知らないというだけで無視されてしまう。私自身、『四季の組曲』の全曲演奏を完全に諦めたわけではないが、実現は難しそうだ。そんなわけで、まずは毎年2月に開催している「NHKラジオから生まれた歌」の中で橋本作品を特集することにした。 とはいえ、歌曲作曲家として橋本がもっとも充実していたのは昭和初期だ。多くの詩人にとっての処女詩集のように、橋本もまた、作曲を始めた当初に、のちに代表作となる才気溢れる作品を多く書いた。大正末期に始まる橋本歌曲の頂点が昭和4年に作曲された『舞』であることは、日本歌曲の世界では定説となっている。 さて、昭和9年からヨーロッパやアメリカを遊学していた橋本は、戦争の足音を聞いて12年に帰国。その後は指揮活動や管弦楽曲の作曲に重きを置くようになった。もちろん、当時の日本作曲界には、まともな管弦楽曲を書ける作曲家は数えるほどしかいなかったわけだが、中でも橋本の才能は群を抜いていた。橋本は、音楽的才能の上でも、時代背景的にも、瀧廉太郎や文部省唱歌の作曲者たちとは土俵が違っていた。 そして、戦時中、彼は東京音楽学校の花形教授として活躍した。橋本は、もはや自分の芸術を追究するだけではすまされなくなっていた。彼の作品は「東京音楽学校作曲」とされる曲の中にも含まれているという。 橋本が帰国する前年、NHKラジオは家族みんなで歌えるホームソングを作ろうと、新しい歌番組『國民歌謠』を立ち上げた。当初は《心のふるさと》《椰子の實》《ふるさとの》といった抒情的な歌が多かったが、昭和12年7月7日の蘆溝橋事件あたりから社会情勢と無縁ではいられなくなった。NHKラジオからは、軍部が制作した歌や、東京日日・大阪毎日新聞公募作品の《露營の歌》、朝日新聞公募作品《父よあなたは強かった》などが放送され始めた。 昭和12年10月13日からNHKの『國民精神總動員強調週間』で発表された《海ゆかば》も、『國民歌謠』で再放送されている。作曲者の信時潔は、東京音楽学校卒業後、ドイツに留学し、大正12年から昭和7年まで同校教授をつとめたが、紀元二千六百年奉祝カンタータ《海道東征》や《海ゆかば》を作曲したことで、橋本と同じように、戦後は作品演奏の機会に恵まれず、作曲家としての評価をも歪められた感がある。 他方、パリでヴァンサン・ダンディに師事した高木東六の作品には《ヒュッテの夜》(國民歌謠)や《あまんじゃくの歌》(ラジオ歌謡)などがあるが、もっとも親しまれているのは《空の神兵》であろう。これまでこの歌を演奏できなかったのは、メロディー譜しかなかったためだが、昨夏、やっとピアノ譜が見つかった。 実際のところ、私は日本音楽を毛嫌いし、「その昔、五体の満足でなかった、主として眼の不自由な琵琶法師や検校たちによって作られたはなはだ個人的な音曲は、みんな陰々滅々型であり〜」(高木東六『ぼくの音楽論』)と書く作曲家の作品など歌いたくはなかった。《水色のワルツ》なら歌わない。だが、《空の神兵》の洗練された和声と楽想の新鮮さに驚かされ、息をもつかせぬ展開に魅力を感じて演奏しようと決めた。 それにしても、高木東六は前掲『ぼくの音楽論』に、TV番組で「邦楽と洋楽の根本的相違をピアノで説明」しようとしたと書いているのだから恐れ入る。もし私がその場に居合わせたら、即座に「平均律のピアノで邦楽の音階を弾けるはずがない」と抗議するだろう。 昭和2年に東京音楽学校を退学した高木は、当時の同校のあり方を全否定し、翌3年パリに留学したわけだが、少なくとも橋本は大正14年に《なやましき晩夏の日に》を、昭和3年には《お菓子と娘》や《斑猫》といったフランス印象派ばりの歌曲を書いていた。橋本が、留学前に、フランス留学組の西條八十や深尾須磨子が書いた詩に近代フランス音楽の書法を生かして作曲していたのは見落すことのできない事実である。 《空の神兵》と同じ楽譜集に、古賀政男の《雲のふるさと》と《勝利の日まで》が入っていた。いずれも有名曲だが、それまではピアノ譜を見つけられなかった。 《雲のふるさと》は、昭和42年の美空ひばり芸能生活20周年のために、古賀が新しい詩を関沢新一に依頼してプレゼントした《思い出は遠く哀しく》の元歌だ。私はこういう演歌調でない古賀メロに出合うと、つい意外性を感じてしまうのだが、そろそろレッテルで判断することを慎みたいと思う。初めて《やすらひの歌》を歌った時も、にわかには古賀の作曲と信じられなかった。『國民歌謠』として取り上げられることを期待して唱歌調に書いたらしいと聞いてやっと納得した。しかし《やすらひの歌》は、結局、戦後の『ラジオ歌謡』で放送されるまで採用されなかった。 その後、古賀の最初期からの作品を研究し、私は彼がいかに柔軟な感性と多彩な音楽的抽斗を持っていたかを知った。今では、日本人の多くが「古賀メロ=演歌」と決めつけてその多様性を認めようとしない上、オリジナルを尊重しないことに憤慨する始末だ。そして古賀も、当時の軍部や放送局の姿勢に憤っていた。 《勝利の日まで》のピアノ譜を入手したので歌ってみたら、どことなくおかしい。オリジナル音源と照らし合わせてみると、サビの部分のメロディーとリズムが全く違っていて、よくよく楽譜を見直すと、「山田榮一編曲」と書かれていた。そこで『古賀メロディー誕生70年記念古賀政男大全集』の解説を見ると、「僕は霧島盤のように作曲したのに、放送局の審査会かなんかで明るい感じに改めたのだと思う。あの時代はそうした事が平気で行われていたから……」と書かれていた。 たしかに山田榮一編曲版は「元気一杯で」(曲想表示)、勇壮な感じがするが、音楽としてメロディーそのものの座りが悪い。「燃えてくるくる心のほのほ」と音階がドレミファソと上昇してきて、「われら」がソソド〜ではブレーキがかかる。そこをラシド〜と突っ走る古賀のメロディーの方がずっと自然だ。しかも、古賀がマイナーコードで書いたフレーズはメジャーに変えられた。さらに、「勝利の日まで」の一回目、古賀はソーラソミと揺らしていたのに、編曲版は無味乾燥にソーソミとした。それまでの音楽的エネルギーを受け止めるためにも、「勝利」という言葉に思いを込めるためにも、ラソという揺りは絶対に必要だ。よって、本日は古賀のオリジナルのメロディーで演奏することにした。なお、もともとNHKに委嘱された《勝利の日まで》は、昭和19年3月にレコード発売された後、翌20年1月の東宝映画『勝利の日まで』の主題歌としても使われた。 《空の父 空の兄》は『國民合唱』の時間に放送された、いわゆる少國民ものの歌である。私はこれまで《僕等の團結》(われらのうた)や《子を頌ふ》(國民合唱)を取り上げてきたが、もっともリクエストが多い《父母のこゑ》はピアノ譜がないため演奏することができない。しかし、佐々木すぐる作曲の《僕は空へ君は海へ》(國民合唱)のピアノ譜を入手できたので、次の機会に取り上げたいと考えている。 後半の橋本作品は、帰国後はじめて書いた『國民歌謠』の《母の歌》から、「東京音楽学校作曲」として書いた《大日本の歌》へと続く。それらの歌は、歴史の証人でもある。昭和18年10月21日に明治神宮で行なわれた「出陣學徒壯行會」に合わせて作られた《學徒進軍歌》や、女性の勤労動員を謳った《戰ふ花》、学童疎開の子供たちがよく歌った《勝ちぬく僕等少國民》。 戦争を知らない世代の私は、古関裕而の作品研究のために《嗚呼神風特別攻撃隊》をはじめとする戦争末期の作品を歌い、こうした作品を知るに至った。そして実際には、敵と向かい合うことなく命を散らせた人が少なくなかったことをも知った。 今さら仮定などしてもはじまらないとわかってはいるが、もし戦争がなければ、橋本は《舞》の路線で日本の歌の可能性を切り開けたのではなかろうか。戦後の橋本が昭和3,4年頃の冴えを取り戻せないまま病に斃れただけに、私はせめてそう信じたい。 |