1項 抜けぬは道理
柴田鳩翁の「鳩翁道話」(天明三年〜天保十年・心学者)にカエルの話があります。
昔、京都から大阪見物に来たカエルと大阪から京都見物に来たカエルが、天王山で出会い、お互いに立ち上がって、めざす彼方を見渡すと自分の住んでいるところと少しも変わらない。それは、カエルの目は背中に付いていて、立ち上がって見たら、後ろが見えていたのです。
それに気づかなかったカエルたちは、これでは行っても無駄だと言って立ち去ったという話です。いくら見つめても目の付け所が違うと間違いを犯すという教訓話です。
同様「鳩翁道話」にある金平糖の壺という話です。
さる町内に婚礼ぶるまいがあった。お年寄が集まり、色々なご馳走が出た。ひとりのある下戸の男が退屈そうにしていたので、亭主が気のどくに思い、「チトお菓子なりとも御取り下されい」と、南京の壺に金平糖をいれて、とし寄の前へ持つてきた。座中も、「これはよいおこゝろづき。どうぞお菓子を召上がられ」と、すゝめられて年寄も「では頂戴をします」と、壺に手首をいれる。そして、つまみ出さうとすると、手首がぬけない。廻して見ても、引つぱつて見ても拔けず、まごまごいていると、回りは「どうなされた」と騒ぎになる。一人が向むかうへ廻まはつて壺を引く。その騒動に座中が一同どっと笑へど、年寄は笑はず、泣き顔になつて、「どうも、ぬけません」と言う。
座は大騷ぎ。「医者をよんでこい。骨つぎではどうだ」と、酒宴の興もさめ果てた。
時にある一人が「そう騷がれるな。司馬温公(司馬光。北宋の文人政治家。)という人が、幼いとき、大勢の子どもとともに、大きな壺のほとりで遊んでいると、一人の子どもが、あやまつて壺の中へはまった。他の子どもはこれを見てにげてしまったが、司馬温公一人は帰らず、手ごろの石をとつて、かの壺へ投げつけた。壺はわれて、子どもの命を助った。今のお年寄のご様子は、この話に似ている。私が司馬温公となって、その古染附の壺が、何ほど高金か品でも、お年よりの腕には代えられない」
と、持っていたキセルで打ち碎た。金平糖が雪の様に飛び散り、ヤレお年よりが助ったと、その手を見れば、ぬけぬは道理。手に一杯、金平糖をつかんでいた。
ありそうな話です。見ている方向や握りしめていることには、自分自身気づかないものです。その気づきにくい私を映し出して下さるのが、仏の言葉やお仏壇の中の仏さまです。
中国の善導大師は「経はこれをたとえるに鏡のごとし」と示されています。生活の中に、ご本尊を頂くとは、自分の心を映す鏡を持つことに他なりません。
2項 神様からの手紙
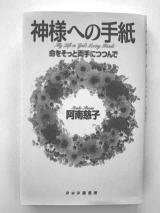
図書館で借りた「生老病死」ーいのちの歌ー立川昭二著に、阿南慈子さんの詩が紹介されていました。彼女は、私と同じ一九五四年生まれ、キリスト教の洗礼を受けた方です。三十一歳で多発性硬化症という難病を発病し、首から下の四肢がマヒし、両眼は失明し、気管支切開で発声も失いない、二〇〇〇年十一月七日に他界しています
早速、阿南さんの著書「神様への手紙」を注文し読みました。エッセイと詩が星のようにちりばめてある本でした。
神様からの贈り物という阿南慈子さん詩です。
車いすのことを悪く言わないで下さい
…
自分の力では立つことさえできなくなった私を
これは速やかに軽やかにどこへでも運んで行ってくれるのですから
ベットのことを 悪く言わないでください
…
背もたれなしでは座ることさえできなくなった私を
背骨に襲いくる痛みとともに
これはやさしく支え受けとってくれているのですから
気管支切開のことを 悪く言わないでください
…
自分では たんを口元まで押し上げる力さえなくなった私を
これは窒息から救ってくれているのですから
人工呼吸器のことを 悪く言わないでください
……
そして何より病気のことを悪く言わないでください
………
神様のことを もっとよくわかるようになったから
そして今まで見えずにいたものが 少し見えるようになってきたから
……
その母の愛をそばで感じて育ったお子さんの豊かな感性にも驚きます。
一男一女の長女、小学生の七星(ななせ)ちゃんは「七星の祈り」でこう綴っています。
神さまもしよかったら、ママの病気をなおしてください。でも神さまがそう思わないのならこのままでもよいです。なぜかというとママがこの病気をちっともいやがっていないからです。かなしんでいないからです。もしこまったことがあれば七星たちがてつだってあげればすむことだからです。
小学六年の時、七星ちゃんが「もしたった一つ願いがかなうとしたら、七星は何をお願いすると思う」とお母さんである慈子さんに聞いたと言います。
そして「貧しい人の病気が治りますようにってお願いするの。普通はみんなママの病気が治りますようにってお願いすると思うでしょう。もちろんママの病気が治ったら、ママも七星もうれしいよ。でも七星にはちゃんとわかっている。ママの病気が治ったと知ったら、他の貧しい病気の人たちが、ママを見て、いいなーとうらやましく思わはる。そんなことになったらママはきっと悲しむね」。
信仰とは、思い通りになることではなく、思い通りにならない現実の中にあっても、失われない尊い世界に眼差しが開かれていくこと。そんな思いを持ちました。
3項 西方寺よりのインフオメショーン
中国の旅ご一緒しませんか
期日 五月十二日(月)〜 十六日(金)〈五日間〉
場所 西安と太原・上海
浄土教の源流を訪ねる
旅行費用 一八四〇〇〇円
成田空港への往復は西方 寺よりマイクロバスにて
添乗員同行
ご老年でも大丈夫です
お申し込みは西方寺まで
西安(昔の長安)
空海さんも行った都です。八〇四年、遣唐使として中国に渡った空海が長安の都に到着しています。
八〇四年夏、四隻の第十六次遣唐使船が難波ノ津(大阪)から出航しました。讃岐の人、満三〇歳の空海は藤原葛野麻呂を正使とする第一船に乗ります。ところが、天候悪く第一船は、本来の目的地である揚子江河口より大きく南方にそれ、寂しい漁村に漂着しました。
(天台宗の祖である最澄は第二船に乗っており無事到着し、後、天台山に入る。残りの二隻は難破)
一行は、地区の官使に、漂着した漁村の管轄先の州都である福州へ行き、入唐の許可を待ちます。ところが二ヶ月余り海上をさまよった空海一行は衣服もみすぼらしく、とても日本国の使者と認めてもらえません。
そこで、許可を求める為、正使に代わり空海が嘆願書を起草します。その嘆願書が余りにも素晴らしい名文であった為、福州の高官の心を捉え入国許可を得ることができたのだそうです。
長安は奈良・平城京の原点です 。現在の奈良は、唐の都・長安(現・西安)をモデルに七一〇年に造営された平城京の原点です。
浄土教の源流の場所
香積寺楼(コウシャクジ)は、 唐時代に善導和尚を記念して建立された、浄土宗発祥の地として知られる仏教寺院です。戦乱や地震などにさらされ、塔の上部三層は崩壊して現在は十層になっている。一九八〇年には、年の善道大市一三〇〇年法要を機に、日中共同で修繕を行い、日中友好のシンボルともなっています。
鳩摩羅什(クマラジュウ・三蔵法師)が阿弥陀経を翻訳した草堂寺もあります。
 クマラジュウ
クマラジュウ
西安では、世界第八番目の奇跡だと言われる兵馬俑抗を見学。中国に一九ヵ所ある世界遺産の一つ。秦の始皇帝を守る等身大の歩兵を中心とした陶俑と陶馬の縦隊。一九七四年、地方の農民が井戸堀作業中に偶然発見さらたものです。
慈恩寺の境内に立つ高さ六〇m余の大雁塔は玄奘 三蔵法師が、二十七才のとき国禁を犯してインドに赴き、四十三才で帰国、持ち帰った多くの経典を翻訳し、納めたところで、現在は七層の建物。
太原では、親鸞聖人が自らの名前とするほど尊敬された曇鸞大師ゆかりのお寺に参拝します。
ご一緒にしませんか。
4項 住職雑感
● 左記掲載のチラシの通り、三月二十五日から五月五日までの間、上野公園の国立博物館において「西本願寺展」が開催されます。私も期間中だけに販売される「展示品・目録本」の購入を楽しみにしています。観覧料は千三百円です。
● 二月八日の「がん患者・家族の語らいの会」のゲスト講師は、朝日新聞記者で自らのがん体験を綴った「がんと向き合って」(晶文社刊)の著者でもある上野創さんのお話しでした。九七年秋に告知を受けてから、手術、化学療法、二度の再発などの経緯を書いた新聞連載をまとめたものです。
新聞の連載は〇〇年十月から翌年の十月まで一年間続き、約千五百通に及ぶ手紙や電子メールによる反響があったといいます。
その上野さんが講演の最後に、「病気が治る・治らないという以外の生きる座標軸が大切です」と語られた言葉が印象的でした。
闘病生活の中、幸福の座標軸は治る治らないだけではないという上野さんの実感なのだしょう。。
病気の中で何に目を付けていくか。一面のカエルの話は昔話ではないようです。
● 西方寺墓地「かしわ青光苑」(柏市布施)があります。共同墓地「れんげ堂」もあります。詳しくは資料をご請求管下さい。
●西方寺ホームページは、上記のアドレスです。検索エンジンに「西原祐治」と入力しても出てきます。
● 西方寺は、設立して十一年の新しいお寺です。遠慮なくご参拝下さい。