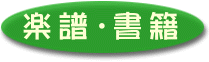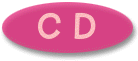藍川由美 (ソプラノ) & 中野振一郎 (チェンバロ)
|
録音:1998年4月21日〜23日(山梨、牧丘町民文化ホール) コロムビア COCO−80861
 コロムビア COCO−80861 |
明治4年の学制頒布で、小学校の教科目として「唱歌」が設けられた。 わが国の音楽教育は、それ以前の日本の民謡やわらべうたを排除したところから始められることになったのだが、教師も教材もないため実施の目途が立たず、文部省は明治8年に伊沢修二らをアメリカに留学させた。明治9年秋よりボストンの音楽教育家メーソンに唱歌を習った伊沢は、明治11年に帰国した後、文部省の御雇教師となって来日したメーソンとともに『小學唱歌集(全三篇)』の編纂にあたっている。 この唱歌集には讃美歌が多く含まれているが、そもそも讃美歌とは世界各地の民謡や愛唱歌に神を賛美する詩をつけた「替え歌」であり、曲自体に宗教色はなかった。 その後も多くの「世界遺産的メロディー」が「日本の歌」として「翻訳」された。こうした「翻訳唱歌」は、日本の音楽文化にどのような影響を与えたのであろうか。 (藍川由美)
|