
[起]Ą 1996年 漆・麻布・銅
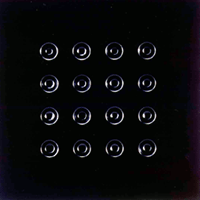
[溜]
シリーズ ―存在する闇 内包する光―より
1999年 木・漆
| METAL ART MUSEUM HIKARINOTANI | |
| 1999年 10月30日 〜11月21日 |
11月の企画展 |
大塚智嗣展 |
−存在する闇 内包する光− |
|
|
会 期 |
1999年10月30日(土)〜11月21日(日) |
作家名 |
大塚智嗣(おおつか ともつぐ) |
作家紹介 |
漆と向き合いはや10年近くたちます。漆に魅せられ伝統という枠から抜け出し,オリジナルな作品を求めても,漆の素材が先に評価されてしまいます。そのなかで修復や蒔絵,漆器の仕事などもしながら漆と今でも向き合っています。 私が漆を離れない理由の一つに樹脂造形と化学塗料という実技の授業を大学で担当しているためもあり,現代の造形及び塗装の基本を教えていますが,ガラス繊維や溶剤などが,制作する人体の健康を著しく損ね,作品が廃棄される場合自然に帰化される事はありません。今は自然素材である漆の良さを実感しながら制作活動しています。 |
作 品 |
立体:レリ−フ 素材:漆,木,鉄 |
制作意図 |
ほの暗い和室に漏れる障子越しの淡い陽射し,格子戸の隙間から忍び込む光の帯,伝統的な日本の建築空間が持つ光と闇の効果に魅せられ,自らの造形に光を取り入れた作品を制作。漆のもつ深い色を闇とし,光源を加えることにより<光>と漆黒の闇としての<漆>をコントラストのなかで表現してきました。 日本の伝統工芸として確立した漆は,表面の加工によって最大限の価値を導き出す事を目的にした技法と思われがちですが,その内側にある形態は漆を引き立たせるために存在します。 今回出品の作品は光源を形態に入れず,漆黒の色を闇とし,内包する形態に光が与えられ自然光またはライティング,存在する時空間により変化する光と闇のうつろいと,漆が本来持つ性質を,見る人にそれぞれ何かを感じてもらえたらと思っています。 |
略 歴 |
1967 福岡県に生まれる 1989 東京芸術大学工芸科入学 1991 平山郁夫賞受賞 1992 五人展(東京芸術大学学生会館)原田賞受賞 1993 東京芸術大学工芸科卒業 サロン・ド・プランタン受賞 1994 個展(巷房,銀座)(AXIS BUSHI,六本木) 若手造形展(横浜銀行本店,横浜) 1995 東京芸術大学大学院漆芸専攻修了 日本漆工協会漆工賞受賞 三人展(ギャラリ−凡,嬬恋村) 漆芸四人展(ギャラリ−おかりや,銀座) あかり六人展(ぎゃらり−すどう,六本木) 工芸科教官作品展(東京芸術大学芸術資料館) 1996 現代漆ア−ト四人展(フジタヴァンテ,千駄ケ谷) あかり展(ギャラリ−イン・ザ・ブル−,宇都宮) 世界の漆 うるし展(フジタヴァンテ,千駄ケ谷) うるし,たのしむ展(丸善,日本橋) 1997 第10回菊池友情展(劉海栗美術館,上海) 1998 朝日現代クラフト展入選 うるし,たのしむ展(丸善,日本橋) 1999 朝日現代クラフト展入選 大塚智嗣展−存在する闇・内包する光− (METAL ART MUSEUM HIKARINOTANI,印旛沼湖畔) 現在 東京芸術大学漆芸研究室講師 |