ホーム | インフォ | 土木 | リンク | お問い合わせ

福島県のがけ条例について
-
はじめに
日本の国土は急峻な地形が多く、毎年台風や集中豪雨による自然災害が起こり、尊い人命や財産が被害を受けています。
近年の都市化により、従来であれば宅地に適しない急傾斜地を開発造成する宅地の供給が行なわれていることも要因となっています。防災の見地から最小限の安全基準を定め、がけに近接して建築する建築物の安全の確認を図ることを目的として定められています。
(がけに近接して建築する建築物の指導指針
がけ条例は、宅地造成等規制法に準じた形で各都道府県の条例で制定しているものです。
都市計画法に基づく開発許可を受けた区域に生ずるがけには適用されません。
|
詳細内容 |
具体例 |
|
第 2条 用語の定義一 が け 地表面が水平面に対し 30度を超える土地で高さが2mを超えるもの二 がけ近接 がけの上下端からからがけの高さの2倍の範囲をいう 三 がけの高さ がけの上端と下端の垂直距離 (3)は、がけに該当しない。
|
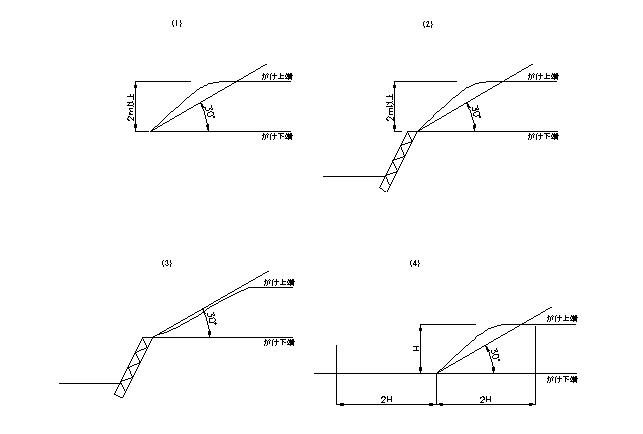 |
|
具体的な規制 第3条 がけ上又はがけ下の建築物の場合建築物をがけ上又はがけ下に建築する場合は、建築基準法施行令又は宅地造成等規制法に定められた技術基準による擁壁等を設置し、その安全を図らなければならない。ただし次の各号の一に該当するものはこの限りでない。 一 がけ上に建築する建築物の基礎は、 RC造とし、がけ下からの水平距離ががけの高さの7/10倍以上離し、かつ、がけの下端と建築物の基礎とを結ぶ線の勾配を30度以下としたもの。二 堅固な地盤を切って斜面とするがけ又は特殊な構造によるがけで安全上支障がないと認められるもの 三 がけ下に建築する建築物は当該建築とがけ下端との水平距離が、がけの高さの 2倍又は20mを越えるもの。
|
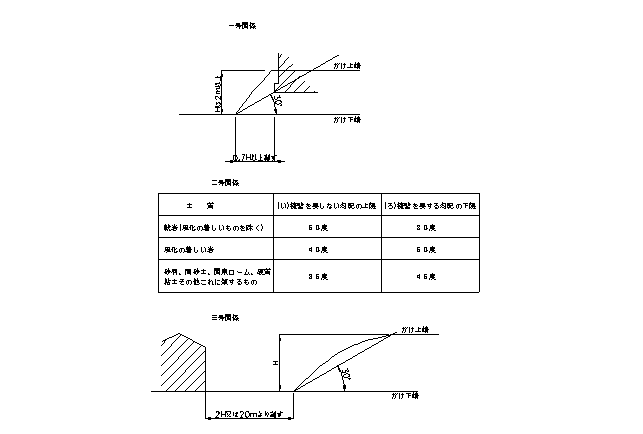 |
|
第4条 既存擁壁等による緩和 がけ近接敷地内に既存の擁壁、土留等がある場合において、これらの構造が RC造、コンクリート間知練積み造、石造等であり、はらみ、沈下及び風化等がないもので次の号に該当する場合は、前条の規定は適用しない。一 がけ上に建築する建築物の基礎は、 RC造とし、がけ下端からの水平距離が、がけの高さの1/2倍以上、がけ上端から1m離し、かつ、がけ下端と建築物の基礎とを結ぶ線の勾配を45度以下としたもの。
|
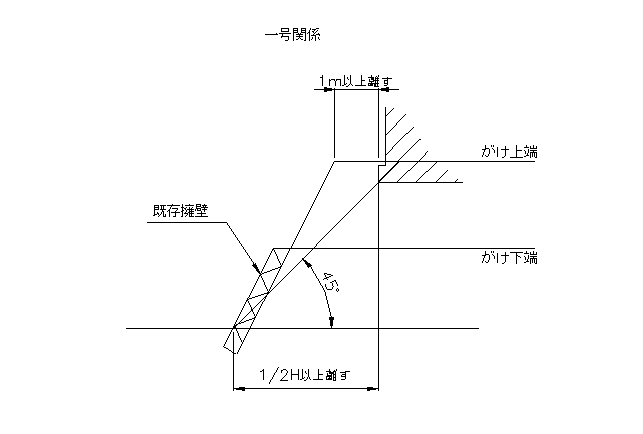 |
| 第5条 がけ内の建築
かけの地表面内に建築する建築物は、政令及び宅造法に定められた技術基準によるほか、次の各号によらなければならない。 一 がけの地表面の形質の変更をする場合において、切土であって当該切土をした土地の部分の高さが 2mを超えるがけを生ずることとなるもの又は、盛土であって当該盛土をした土地の高さが1mを超えるがけを生ずることとなるものは、擁壁を設けなければならない。この場合において擁壁の基礎は、がけ下端と当該擁壁の基礎とを結ぶ線の勾配を水平面に対し30度以下とした部分に設けなければならない。二 切土又は盛土により生ずる地表面は、芝張り、モルタル吹き付け等により当該地表面の崩落防止の措置を講じなければならない。
|
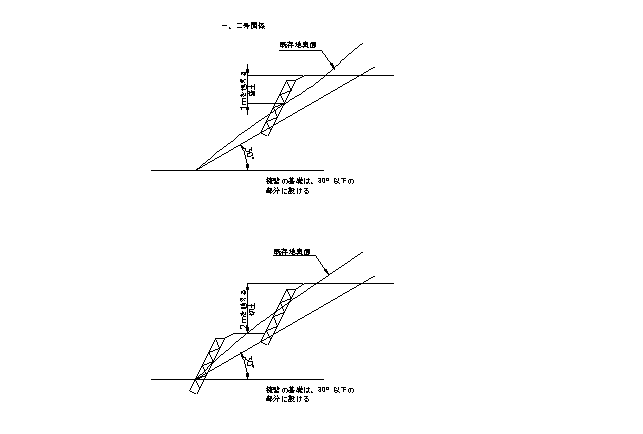 |
|
第6条 擁壁の構造 一 高さが 3mを越える練積み造擁壁は、原則として谷積みとすること二 高さが5mを越えるRC造擁壁は、構造計算をするにあたり、地震時の水平力を加算すること。三 高さが 0.6mを越え、2m以下の擁壁は、RC造、重力式コンクリート造または練積み造とすること。
|
第7条 排水処理
(推奨規定)
一 がけ上の排水処理は、がけ肩にコンクリート敷き、アスファルト敷き等を行い、その保護をはかること。 二 がけ地表面に排水処理施設を設ける場合、その周辺の崩落を防止するため、適切な方法により措置を講ずること。 三 がけ下の排水処理は、がけ尻にコンクリート敷き、アスファルト敷き等を行い、その保護をはかること。
|
| 第8条 二段擁壁
2段擁壁を設置する場合において、下段擁壁の下端と上段擁壁の下端とを結ぶ線の勾配が水平面に対し、30度を超えるときは一体の擁壁とみなし、第4条第1号の規定を適用する。
|
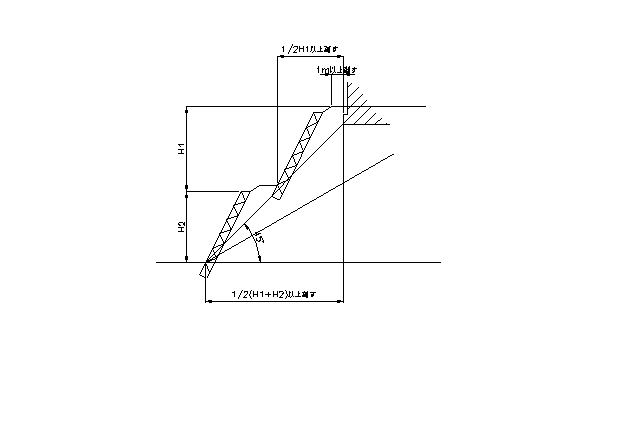 |
※ この擁壁は、高さが2mを超える場合、工作物の確認申請が必要で、1箇所で2種類(重力式擁壁と、積ブロックなど)申請の場合
それぞれ申請する様指導されました。
※ 地震時の安定計算が高さ5m以上から必要なのは、道路土工指針(高さ8m以上)より厳しい条件になっています。
