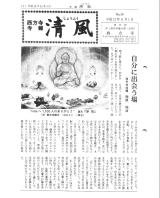地下鉄に乗ると、向き合い側に若い女性が座りました。まず耳にヘッドホーンを当て、音楽を聴きはじめます。次にバックからマンガ本を取り出し開らくと、続けてあめ玉を口に放り込みました。口と目と耳のフル活動。これが移動しながらですから、見ている方が、目を見張りました。 ながら族という言葉が生まれて久しい時がたちます。音楽を聴きながら勉強する。それが、音楽を聴き、食べながら本を読むとなり、次に、歩きながら音楽を聴き、本を読んで口に物を入れるとなる。二つが三つに、三つが四つにと増えて現代に至っています。
まだこの組み合わせは理解できます。過日、新聞に次のような出来事が紹介されていました。場所はワシントン大学です。
大学のキャンパスのトイレは、個室のドアの上下が大きく開いており、中の様子が分かる。授業の合間にトイレに行くと、便器に座った男のスニーカーをはいた足が見えた。足の側にポテトチップの袋と大きな箱が置いてある。その個室から「ボリ、ボリ」「クシャ、クシャ」という音がきこえる。驚いて目をこらしてきていると、牛乳パックが彼の手から床に置かれたのだそうです。用を足しながら食事をしていたのです。
さすがに日本ではと思います。でもこうした光景に違和感を持たなくなる時代が来るのかも知れませ。
「忙しい」という文字は「こころを亡ぼす」と書きます。まさに、忙しさが人の品位を亡ぼしていく。そんな思いを持ちます。
忙しければ忙しいほど、逆に癒し系の本やグッズが売れます。人は動と静のバランスを保ってこそ、平常心が保てるからです。
忙しい現代。今もっとも贅沢な場所は、沈黙の場所だともいえます。お仏壇やお墓を先祖のだけのもとそせず、自分が自分に出会う場として、生活の中に、その意義を見直す時がきているようです。
![]()
2項・3項
タイトル 亀さん喜ぶかなー
私の手元には、記念の念珠がふた輪あります。一つは、故東條英機が使用していた念珠。もう一つは、父からもらった念珠です。
故東條英機は、昭和二十三年十二月二十三日、巣鴨のプリズムでA級戦犯七人の一人として、処刑されています。 東條家は本来、神道でした。しかし、最後は浄土真宗の念仏を喜ぶ者として終わっています。その一部始終は、巣鴨で刑務教誨にあたった花山信勝著「平和の発見」に詳しく記されています。
勝子(妻)へは、精神的打撃だろうが、仏の大慈悲を頂いて天寿をまっとうせよ。『歎異抄』の第一章は胸につく、最後になると称名とこれだけで充分だと思う。…
日も月も蛍の光さながらに
行くてに弥陀の光かがやく
(平和の発見より)
処刑の最後の日、英機氏と信勝氏との会話の一部です。
七人の死後、それぞれの遺族たちは、縁のある郷里に隠れるように身を置きます。しかし、国賊と非難され、歓迎されない厄介者として扱われます。
勝子夫人は晩年、「私も、子の母であり人の妻です。子や夫を失って悲しくないはずはありません。たまたま子を戦争では失わなかったものの、その悲しみは痛いほど分かります。ですからみなさんが、私を恨んで心が安まるのなら、と、じっと黙って耐えてきました」と述懐された通り、家族は就職も出来ず、じっと耐えていく生活であったようです。
戦争犯罪人として処刑された人は、国内国外合わせて千六十八名にのぼります。その遺族は、戦争のために家族を失った者で組織する「遺族会」にも国賊扱いをされ入会が許されなかったようです。
昭和二十九年、戦犯の遺族で「白菊会」が結成されます。しかし、同じ戦犯の遺族でも、命令した側と命令された側という意識が根底にあり、その「白菊会」でも、A級戦犯の遺族たちは肩身の狭い思いをしたと言います。
そんなこともあってか、A級戦犯の遺族だけで「七光会」をつくり交友を持ちます。それがいつの日か、毎月二十三日、用賀の東條邸に集まり、茶話会がもたれるようになりました。
昭和五十五年十二月、築地本願寺で故東条英機の三十三回忌法要が営まれます。そのご法事を契機として、毎月二十三日(東條英機の命日)、用賀のお宅で、月参りが始まります。同五十七年五月二十九日、勝子夫人が亡くなりまでの一年半、「西原さんに」という要望もあり、私が専属で、その茶話会とご仏事に出勤しました。毎月のご仏事は、勝子夫人が亡くなり、用賀邸を手放した後も、ご次男の輝男の三鷹のお宅で続けられました。
その間親しく、東條家の方々と仏縁を頂き、ハワイに行ったときは、アメリカ人と結婚した英機氏の末女君枝さんご家族と昼食を頂いたことも楽しい思い出です。
さて念珠の話です。その用賀のお宅には、仏壇があり、その中には色々なものが収められていました。処刑の直前、七人が手錠をしたまま書いた七名のフルネイムのサイン。昭和五十三年十月、靖国神社合祀に際し、神社から下ったを名前が記されたお札。等々。邸宅を壊すに当たって、ご次男の美代子夫人より、仏壇の中の不要となる品の処分を頼まれました。その中には、靖国神社の先のお札や、諸々がありました。その折、記念に頂いたのが、いま言うお念珠です。
昭和二十九年生まれの私には、戦争の思い出はありません。ただ東條家との数年間のご縁の中でお聞きした、戦犯家族の戦後の話、三十三年を過ぎても、ひっそりと営まれていた戦犯家族が集う茶話会、これが私が触れた、かすかに残る戦争の傷跡でした。
記念に頂いたお念珠は、私の手元にある戦争につながるただ一つの遺品でもあります。
もう一つのお念珠は、父にもらった念珠です。
ある日、実家に行くと父が「形見に何か買ってやりたいが、袈裟が良いか、衣が良いか」と聞きます。父はその数ヶ月前に食道ガンを患い、長い延命は期待していない状態でした。その場でのやりとりは以前ご紹介したので省略します。
結局、念珠を買ってもらうことになりました。念珠に決まってから数ヶ月、「まだ買ってないのか。まだ買ってないのか」と、父も私がもとめてくるのを待ちどうしい様子でした。
今年の三月、京都へ行った折、念珠の専門店でもとめてきました。それは鼈甲(ベッコウ)の念珠です。 京都から帰って父に見せると、しげしげと念珠を眺め触っていました。そして念珠を眺めながら「はあ、亀さんか。亀さん喜ぶかなー」といいます。となりで母が「それは喜ぶよー。お念仏のご縁に遇うのだから」と、その念珠を庇護し、父に諭すように言います。私はその父母の会話をそばで楽しく聞いていました。
後で思ったことです。亀さんは喜ぶはずはない。いくらお念珠となり、仏縁を待ったからと言って亀さんは「十方衆生」です。「十方衆生」は、我が身が一番可愛いのです。仏様よりの自分の命を大切に思うのが、私や亀の習性です。
しかし、そうした習性から逃れることの出来ない亀さんが、その存在の有り様を否定されることなく、阿弥陀如来の大悲によって満たされていく。その大慈悲に、いま甲羅の念珠となっていま出遇っている。この事実は亀さんの何百万年かの歴史の上で、ただ事でないことが起こっているのだと思います。この阿弥陀如来のお慈悲は、亀さんにしか分からない仏縁として、きっと亀さんに届けられているに違いありません。
そんな思い出の鼈甲のお念珠です。この念珠は、ご法話でこの念珠を自慢するときと、西本願寺の即如ご門主の随行で、各地に行くときだけに持参しています。
私がこの世を去った後、父の「亀さん喜ぶかなー」の逸話と、私のご門主の随行の思いでが籠もっている念珠として、子供たちに伝わるのだと思います。
![]()
4項 タイトル 住職雑感
産経新聞(夕刊)にコラムを書いています。六人の宗教者が、同じ題で、コラムを書きます。そして一日、二人が並んで掲載されます。
隣にどなたがくるかは、一つの小さな楽しみでもあります。 九月は、「収穫」という題で、お隣さんは、渋谷にある聖ヶ丘教会の牧師・山北宣久三でした。その中に面白いたとえ話が織り込まれていました。まずは紹介します。
収穫も天気次第ではたまらないと、ある農夫が神に直談判した。「私の天気をコントロールさせて下さい。天気に一喜一憂しつつ収穫をめざすのはたまりません」
神はこの願いを許可しました。やったーと言って今日は雨、明日は晴れ、このあたりで曇りと自由に天気を操り、まさに脳天気、気楽に収穫への向かっていった。
事実、その年は麦の収穫は空前でした。ところがなんと、穂の中に一粒の麦も入っていませんでした。それもそのはずです。農夫は風を吹かせることを忘れていたのでした。風が吹かず花粉が散らないため、交配ができず、収穫はゼロだったのです。
これはキリスト教の宗教改革者マルチン・ルターが作った話だそうです。
ルターの話の最後は、「とかく神の手にあるものを奪おうとする者の結果はかくのごとし」と結んでいるとのこと。
この話を通して何を味わえるか。みんなで話し合ったら面白そうです。
Aさん『天の摂理こそ神そのものだ』。Bさん『不確実性こそ人の文化の源だ』。Cさん『人間の分限を知ることが大切だ』等々。
さて私は次のことを味わおうと思います。物理学・天文学や科学技術の発展は、人間が全く新しく創造したものではなく、すでに自然界に原理や内在性のこととして存在していた。それを人間が実験や計算また望遠鏡などによって発見したに過ぎない。自然への畏敬の念を常に失ってはならない。常に畏敬の念を持つならば、ルターのように『神の手にあるものを奪う』といった、自然(神)と対立した考え方ではなく、自分で自然をコントロールしながら、そこに自然の恵みを見失うことなく過ごすことが出来るように思います。
西洋は、自然と人間。神と私。 善と悪。と言った具合に、物事を分ける考え方が根底にあるようです。東洋は、融合、円融と言うように、全体の中に自分を見、海の水がすべての川を一味にするように、善悪を融合する、ダイナミックな考え方があるようです。
みなさんはルターのたとえ話から何を味わいますか。
次号は平成13年3月1日号です