

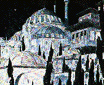
イスタンブールは目の快楽のために建造されたかのように見える。幻が消えてしまわぬかと恐れ、人々は記憶に、現実とは思えぬ事物を刻み込む。
フォルバン
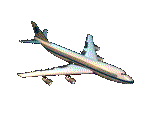

ホテルで朝食をとった後、旧市街へ。

ムスタファ・ケマルは1881年に現在のギリシャ、サロニカで生まれた。イスタンブール陸軍大学で職業軍人として教育を受け、バルカン戦争(1912-1914)では特校として勇敢に戦い、頭角を現す。第一次世界大戦(1914-1918)のさなか、イギリス軍がゲリボルを攻撃した時には、副司令官として英仏連合軍を撃退。そして1919年5月15日、北部方面軍総監に任命され、19日にイスタンブールからサムスンへ上陸する。ここからトルコ革命は始まる。当時イスタンブールではメフメット6世がスルタンとして支配していたが、その政府は連合軍の傀儡にすぎず、民主主義活動はアナトリア中心部を主体としていた。ケマルはアマスヤ入りし、ここでトルコの独立を宣言する議定書に署名をした。
7月23日エルズルム会議が開かれ、各地域から代表者が集まり、ケマルを議長として選出する。トルコの独立と統一を護り、帝国滅亡の際には臨時政府が組織されることが、会議で承認された。9月4日シワスでの国民会議においてもケマルは議長に選ばれ、連合国及びイスタンブール政府に対抗する姿勢を明らかにした。翌年の4月23日彼はアンカラでトルコ大国民会議を開会し、主権在民を旨とする臨時憲法を採択し、議会が国民を代表して、立法・行政の権限を持つことを決定した。
サカリヤ川の会戦(1921年8月)ではアナトリアに侵入してきたギリシャ軍を破る。1923年7月24日に調印されたローザンヌ条約で、大国民会議はトルコ代表として迎えられ、トルコの国境が定められた。そして1923年10月29日、アンカラを首都にトルコ共和国が誕生し、ケマルは初代大統領となった。
トルコの革命の特徴的な点は、アタチュルクが何よりもトルコの西欧化を図ったことに尽きるだろう。それにはまず政教分離が行われなければならない、と彼は考えた。一夫多妻制の廃止、フェズ(トルコ帽)着用の禁止、スイス民法を模した新しい法律の制定、ラテン文字の採用、男女同権の実施など、殆どの政革がイスラーム教からの分離を意味するものだった。イスラーム聖法を廃止したのは、イスラーム国家(国教ではないがトルコ国民の大部分はイスラーム教徒である)でトルコだけである。法律はイスラーム教で神聖なものとされるから、いかにこの改革が画期的であったかがわかる。姓の使用も義務付けられ、ケマルは議会の提案により、ケマル・アタチュルク(トルコの父)と名乗ることになった。
アタチュルクの外交政策のスローガンは「国内に平和を、世界に平和を」である。彼は軍人として才を発揮し、勇敢に戦ったが、それは国土を守る為であって侵略する為ではなかった。イスラーム教が国教でなくなったことに反発を覚えた人々は、決して少なくなかったが、当時のトルコの状況は亡国寸前で、今までの法律や習慣を見直さなければならない時期に来ていた。アタチュルクは、まさにトルコの救い。現在のトルコの発展があるのも、彼が土台を作ったからこそである。
アタチュルクに関して記述する時、大文字のO(トルコ語で彼)が使われるそうである。彼は"特別な何ものか"なのである。
アタチュルクは1938年11月10日9時5分に57才で亡くなった。彼が息をひきとったドルマバフチェ宮殿の彼の部屋の時計は、9時5分のままである。11月10日のこの時刻には、あらゆる交通機関がストップして2分間の黙祷が捧げられる。
 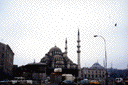  |
|
イエニ・ジャミイ ガラダ橋のたもと、旧市街側にある大きな寺院。メフィット2世の母が1597年、建築家ダヴート・マーに建てさせ、メフメット4世の時代に完成した。 |
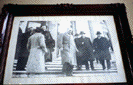 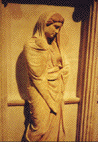 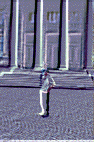 |
|
イスタンブール国立考古学博物館 オスマン・トルコ時代に英・仏により発掘調査が盛んに行われ、大半は各国に持ち去られ博物館に収められてしまった。しかし、1881年以降の出土品はすべてイスタンブールに集められており、アレキサンダー大王の石棺をはじめとした、ギリシャ・ローマ時代のコレクションは世界的にも評価が高い。 |
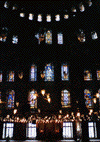 |
ブルー・モスク(スルタンアフメット・ジャーミイ) イスラム教モスク。1609-1616年、スルタン・アフメット1世によって建造された。優雅なドームと半ドーム、それに6本のミナレット(尖塔)が美しい調和を見せている。当時、ドームの大きさやミナレットの数、高さは、それを建造するスルタンの権力の象徴だった。他に類を見ないモスクにするため、アフメット1世は建築家メフメット・アーに「黄金(アルトゥン)のミナレットを造れ」と命じた。ところがアーは「6本(アルトゥ)のミナレット」と聞き違えたのだという。偶然の所産ではあったが、その結果、世界で唯一の6本のミナレットを持つモスクが誕生したことになる。モスクの四隅にある4本のミナレットには3層のバルコニーが、中庭の2本のミナレットには2層のバルコニーが付いている。 |
 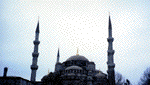 |
シュレイマニエ・ジャミイ オスマン帝国が最も繁栄した時期に君臨したシュレイマン大帝が造らせた寺院。1557年に完成した大聖堂。建築家はトルコ最高といわれるミマル・スィナン。彼は初めて4本のミレナットをつけ、当時の最高技術を使って59m×58mの床面に47mの円形屋根をのせた。その大きさもさることながら、内部の装飾も美しい。 |
 |
ヴァレンス水道橋 ヴァレンス帝時代の378年に完成した水道橋。トルコ語名は灰色鷹のアーチという意味で、現在もまさしく旧市街のアタテュルク大通りをまたぐように、翼を広げた格好で建っている。かつてはその長さもおよそ1km近くに及んでいたという。 橋は2階建で大都市コンスタンティノーブルの給水システムの重要な役割を果しており、その水は地下宮殿へと注がれていたといわれている。 |
 |
イスタンブール大学 歴史的にみると、大学の創設はメフメット2世によるコンスタンティノーブル征服直後の15世紀。オスマン帝国時代にも神学、哲学、法学、薬学、科学などの学部があったという。但し、現在の敷地は当時、旧宮殿と呼ばれる建物があった場所で、退位したスルタンの妻達が生活していた。現在の建物は、19世紀フランス人建築家オーギュスト・ブルジョワによる建造。一部は旧陸軍省の建物等にも利用されていた。 |

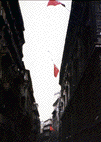
 |
ガラダ塔 新市街のランドマークともなっている67mの塔。6世紀初めに灯台として利用されていたものを、14世紀に入り周辺に居住していたジェノバ人がビザンツ帝国への監視塔に建造したと考えられている。その後、牢獄や、天文台などにも利用された。 現在残っているのは14世紀からのもので、一度火事で焼失し、再建されている。 |
 |
ペラ・パラス・ホテル アガサ・クリスティは「オリエント急行殺人事件」を執筆するために、このホテルの411号室に滞在していた。現在この部屋のドアには"アガサ・クリスティ"というネームプレートが掛かり、室内には彼女が使った机や棚が、当時のまま保存されている。宿泊者は室内を見学することができる。 |
    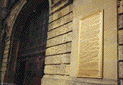  |
|
ハイダルパシャ駅は、イスタンブールのアジア側起点駅。ここからはトルコのアジア側への列車が出ている。 駅舎はドイツ人の設計による、ネオ・ゴチック様式。内部には彫刻が施されておりとても美しい。特にチョコレート色の扉や窓口に、まだ木製の部分が多く、歴史を感じさせてくれる。高い天井、広いホールにもどことなく落ち着きが感じられ、加えて駅独特のざわめきが旅情をさそう。 |




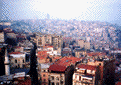
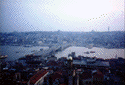

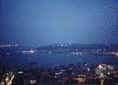
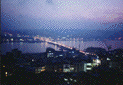
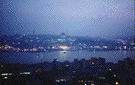


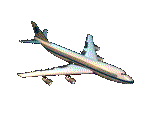
成田着 10:10 定刻