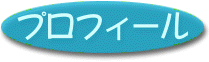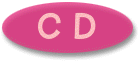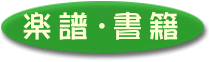|
──三善 晃の歌に出あって──
藍川 由美
合唱曲『おてわんみその歌』について、作曲者はこう書いている。 おてわんみそとは、おてんば、わんぱく、みそっかす(あるいはみそっちょ)のこと。
自分がわんでみそのガキだったから、ユウトウセイとかオスマシは不倶戴天の敵。 ここでも「困った子供たち」の替え歌に大いに共感して――つまり、懐かしんで――大人が眉をひそめるにちがいない詞にf(フォルテ)をつけてやった。 (1979・三善 晃)
これを読んだ時、私は自他共に認める「おてみそ」だった少女時代を思い出した。
三善晃先生は東京生まれの東京育ちだが、三善家父祖の地は讃岐ではないかと思う。 直接お訊きしたわけではないけれど、1991年に丸亀市猪熊弦一郎現代美術館がオープンした際、丸亀市ゆかり(祖父が丸亀市長)の芸術家として三善作品によるコンサートが行なわれた。 私が生まれ育ったのは丸亀市の隣の宇多津町で、我が先祖は江戸時代後半にこの地へ赴任してきた。 香川県立坂出高校を経て東京芸術大学に入学した私が初めて三善先生にお目にかかったのは大学三年の時で、約10分の演奏時間を与えられる学内演奏会で歌曲集『四つの秋の歌』を演奏するためにレッスンをして頂いた。 三善作品の美しさに魅了された私は、その後も先生の作品を演奏させて頂くたびに御指導を仰いだ。
そして私は修士及び博士課程で日本歌曲を専攻し、いわゆる「現代音楽」を演奏するようになった。 しかし芸大でも日本の声楽界でも、オペラより「日本歌曲」を演りたがる歌い手は異端視された。 なぜ自国の音楽作品を演奏することが異端視されるのか。 なぜ日本の歌が外国のオペラや歌曲よりも低く見られなくてはならないのか。 二十代から三十代にかけて自問自答の日々が続いた。
明治に唱歌教育が始まって百年余り、日本の歌が未だ閉塞状態にあると感じた私は、実態を把握するために五線譜で作曲された日本の歌の歴史を辿ってみることにした。 すると最初期の官製唱歌こそ外国曲に日本語の歌詞をあてていたものの、邦人が作詞・作曲した歌の多くは‘言葉にふしをつけたもの’だとわかった。 日本の歌では、唱歌であれ、童謡であれ、前衛的な技法を使った歌曲であれ、逐語的にメロディーをつけ、伴奏をあしらうのが常套手段のようになっていた。 これは‘ふしに言葉をつけて歌う’「和歌披講」と逆のやり方だ。
そのどちらでもない途を三善晃は選んだ。 日本の歌に限らず、メロディーだけでもサマになる歌は少なくないが、三善作品の場合はすべての音が定位置にピタッと填らないと曲にならない。 先生の仰る「音のポエジー(作詩法)」とは、詩の世界や心象風景の音像化なのだろうか。 それにしても歌とピアノが複雑に絡み合う先生の歌曲を演奏するのは容易ではない。 私は一時期、「三善晃の音楽」が凡庸な演奏を拒絶しているように思え、近寄り難くなった。 それが、ある時、従妹が使っていた教科書で『栗の実』という歌を見つけて変わった。
1970年代後半に教科書用の教材として書かれた作品の中で、私はとくに詩・曲とも三善晃作の歌が好きになった。『栗の実』では、三つ目の栗が三年後に芽を出し、やがて栗の木になる。 そこに作者の温かいまなざしが感じられた。 私は近代日本の歌のカタログを作るために、歌曲のみならず、唱歌、童謡、流行歌などにまで手をのばしてきた。 そのため表面的には現代の日本歌曲から離れてしまったように見えるかも知れないが、同時代の作曲家の作品を演奏することを最重視する基本姿勢に揺らぎはない。 栗の実はいつか必ず栗の木になる。
とはいえ、三善先生に最初に御指導いただいてから既に三十年近い歳月が過ぎた。 歌い手としては決して短い時間ではない。 やっと先生から頂いた言葉が実感に変わり、「三善晃の音風景」に立ち会うことを許されたのかも知れないという気がして、今年2月、レコーディングに踏み切った。 だが、「おてみそ」の分際でそうそう立派な演奏家になっているはずもない。 9月にはそのほとんどを録り直すことになった。 ただ、ここまで音楽への情熱を持ち続けられたのは、先生が私ごとき者のために貴重なお時間を費やして下さったことへの感謝の気持ちがあったからだと思う。 また、私の声楽の師匠である畑中良輔先生や奥様の更予先生、そして瀬山詠子先生との御縁も大きかった。 三善先生がNHKの委嘱で1954年に書かれた最初の歌曲集『高原断章』は1955年3月に畑中更予先生によって放送初演され、歌曲集『白く』は1962年秋に瀬山詠子先生が初演された。
『聖三稜玻璃』
1962年、大蔵担子さんの委嘱に依り作曲。 同年11月のリサイタルで初演された。
前年からこの年にかけては、歌曲集『白く』を書いているので、詩も、音のポエジー(作詩法)も前作とは全く異なったものをこころがけた。
大蔵さんの歌ごころと謂おうか、静かに詩をつぶやくうちに、心象のドラマが形を持ちはじめる。 これは内面に向かって歌われる一連の祈りである。 ピアノの、小さく冷たいフィギュレーションも、そのエトスの中で息づかねばならない。 (1971・三善 晃)
『四つの秋の歌』
1963年、池田弘子さんの委嘱に依り作曲、同年10月のリサイタルで初演された。
高田敏子さんの詩と池田さんの心に誘導されて、簡明なカダンスを織りつづるピアノと、歌いやすい旋律をこころみた。 それだけに、歌の哀感と優しさとピアニズムの色彩的なニュアンスに、心のすべてがかけられよう。 (1971・三善 晃)
『抒情小曲集』
1976年、酒井義長さんのために書いた。
五つの詩は、それぞれ一つの核を抱き、何物の支えもなしに感情の水中に定位しているが、私のカダンスはその周囲をめぐる、小さな水流である。 その韻律もまた、すべて、くれないの、れいしの核へ、モレンドしてゆかねばならない。 (1978・三善 晃)
『高原断章』
平井康三郎先生のお宅で、歌い手の人たちの伴奏を始終していたが、畑中更予さんもその一人だった。 その後いままで、畑中さんの音楽から、どれほどの教えをいただいたか、測り知れない。 この曲も、初演時に、それで手直しした。 (1979・三善 晃)
『白く』
左川ちかの詩に不思議な絶望がある。
失つた声 向ふ側の音 見えない花
そして もう近くに居ない夏
しかしそれは艶冶な装いにくるまれ
ほとんど 誇り高きものの姿をして居る
微量の毒を含んだ刺が 老人を嗤い
少女らの指先に虚しい情感を植え
私を刺した
六〇年の初夏に、私の周囲も左川ちかの詩語に似かよって来、いつのまにか、作曲の手続き一切が決められてしまった。 (1969・三善 晃) | 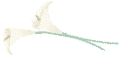 2005年11月13日(日) 19:00〜/東京文化会館小ホール
2005年11月13日(日) 19:00〜/東京文化会館小ホール
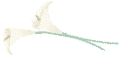
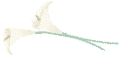 2005年11月13日(日) 19:00〜/東京文化会館小ホール
2005年11月13日(日) 19:00〜/東京文化会館小ホール
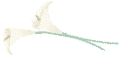
 050−7511−8457
050−7511−8457